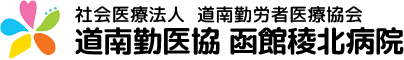理念・基本方針
理念
どんな障がいがあっても、その人らしく過ごせる社会へ
基本方針
- 科学的な根拠に基づいて、患者・利用者とその家族に寄り添ったリハビリテーションを実施します。
- 多職種と協働し、心身の機能の回復とADLの向上、生きがいを追求します。
- 自己研鑽に努め、リハビリテーション技術の向上を図ります。
- 地域の医療・保健・福祉との連携を図り地域のリハビリテーションの発展に努めます。
- 安全管理に努め、安心できるリハビリテーションを提供します。
- スタッフ全員が幸せに働けて、全力で患者さんや課題に向き合えるチームを創ります。
リハビリへのこだわり
どんな障がいがあっても、その人らしく過ごせる社会の実現を目指して、私たちはすべての人が自分の個性や希望を大切にしながら、安心して暮らせる環境づくりに取り組んでいます。この理念は、障がいを持つ方々が自分らしく生活を営み、充実した日々を送るための土台となるものです。
私たちは、科学的根拠に基づいたリハビリテーションを提供し、患者さんやご家族に寄り添いながら、心身の機能回復と日常生活動作の向上を支援しています。個々の状態やニーズに応じたプランを立て、移動や排泄、食事など、その人にとって大切な「生活」を支えるためのリハビリに力を注いでいます。
また、医師や看護師、リハビリ専門職、福祉職、栄養・薬剤の専門職など多職種が連携し、より効果的で包括的な支援を行っています。私たちは常に知識と技術の向上に努め、安全で質の高いサービスを提供できるよう努めています。
地域社会との連携も大切にしており、退院後も安心して暮らせるよう、地域の医療・福祉機関と協力して継続的な支援を行っています。
すべての人が自分らしく生きられる社会のために――。私たちは、情熱を持って日々の実践に取り組んでいます。
役割と機能
科学的な根拠に基づいて、患者・利用者の立場を考慮したリハビリテーションを実施します。多職種と連携し、心身の機能との回復を支援します。
回復期リハビリテーション病棟
当院の回復期リハビリテーション病棟では、脳血管疾患・大腿骨頚部骨折・腰椎圧迫骨折・廃用症候群等の患者さんを発症から出来るだけ早く受け入れています。
入院時には、多職種合同で評価をおこない、1~2週間以内に多職種合同で患者さんの退院に向けた打ち合わせを実施しています。
主治医はリハビリテーション専門医が受け持ち、患者さんの退院先に向けた支援にとどまらず、患者さんご家族や取り巻く方々の不安に対する支援や社会参加まで見通した支援をおこなっております。
また、365日1日2時間以上のリハビリ、病棟生活でも集団起立訓練やトイレ誘導、食事時の離床等、活動量を高める取り組みを全力で実践しています。
地域包括ケア病棟
地域包括ケア病棟は、病院での治療後に患者が自宅での生活に戻れるよう、リハビリテーションや生活支援をおこなう病棟です。専門チームが患者の自立をサポートします。
当院では、病気や怪我で体の一部が上手く動かせなくなったり、日常生活で必要な動作が難しくなったりすることを防ぐために、早期からリハビリテーションを始めます。リハビリテーションは、日曜・祝日を除いて提供します。リハビリテーションを続けることで長い間動かないことによって起こる「廃用症候群」の発生を防ぎます。それにより、運動機能の回復、日常生活動作(ADL)を維持したり向上させたりすることです。
最終的には、患者さんが元の生活に戻れるよう、また住み慣れた地域や退院先にスムーズに戻れるように、リハビリテーションを提供します。
外来リハビリテーション
外来リハビリテーションは、病院やクリニックに通って、専門のスタッフから身体機能の回復や向上のための訓練を受けるサービスです。
在宅生活や仕事をしている方々のために、痛みの管理や運動機能、日常生活動作(ADL)の改善と維持を目指して、自主練習と動作の指導をおこないます。また、自動車運転のサポートや、飲み込みの障害、言語障害、認知機能の障害がある方への支援もおこないます。
リハビリテーション部の活動
- 【資格取得】3学会合同呼吸療法認定士(PDF:452KB)
- 【内部研修】2026.1.24 2025年度第2回管理者研修に参加して(PDF:370KB)
- 【内部研修】2026.1.23 身体障害者手帳について(PDF:462KB)
- 【学会参加】2026.1.10-11 第14回日本理学療法教育学会学術大会in東京に参加して(PDF:544KB)
各科について
理学療法士

理学療法士(PT)は寝返り・起き上がりなどの基本動作、歩行などの移動動作の自立を目標に、筋力・バランス能力・持久力の向上を図り、可能な限りの機能向上を目指します。そのほか関係職種と共同し、福祉用具の選定やご家族に対する介助指導、住宅改修の提案など、安心して社会復帰できるようサポートしています。
目標
- リハビリテーション医と理学療法士チームで患者の早期歩行について追求する。
- 客観的な評価を定期的におこない、Evidenceに基づいた治療をおこなう。
- 屋外歩行や階段昇降などの実用的な歩行獲得を目指す。
作業療法士

作業療法士(OT)は日常生活が困難となった患者様に対して、生活に必要な食事・トイレ・入浴・着替え・調理などの練習や動作の工夫をおこない、生活能力向上を図ります。
実際の生活場面に直結する能力の獲得を目指してご自宅での動作練習を行ったり、手工芸等の作業活動を用いたりします。
目標
- 患者さんの身体・精神面の状態を評価し、目標設定・プログラムの立案をおこない、生活に即したリハビリテーションを提供する。
- 多職種と協力し、患者さんの生活再建を目指す。
言語聴覚士

言語聴覚士(ST)は失語症(うまく話せない)・構音障害(呂律がまわらない)の患者さんに対して日常生活に必要なコミュニケーション能力の改善を目指します。
また嚥下障害(うまく食べられない)の患者様に対して、嚥下造影検査(VF)も含めた専門的な評価・治療をおこない、安全においしく食事がとれるよう支援します。
目標
- 患者さんの「食べる」を支援する総合力のアップを図る。
- 事故の専門性を高めつつ業務効率をUPさせ、患者さんの生活の質向上へ努める。
- 自分たちの治療成績を振り返るとともに、院外へ発信していく。
研修について
研修目標
- 科学的な根拠に基づいて、患者さんの立場を考慮したリハビリテーションを提供する。
- 職種の専門性を発揮し、チーム医療の中核を担うセラピストを育成する。
- 急性期・回復期・維持期を経験し、総合的な力を持ったセラピストを育成する。
- 民医連職員としていのちと平和を守る運動に参加する。
研修概要
※リハビリテーションマニュアルより抜粋
- 初期研修は5年とする。中堅研修は5年とする。
- 研修はリハビリ技士全体で取り組む研修とPT・OT・ST独自の研修の2部で構成する。
- 研修は研修委員会で作成した年間計画と研修要綱を基におこなう。
- リハビリテーション部の総責任者はリハビリ部長が担う。統括責任者は科長が担う。各部門の責任者は各主任が担う。
- 初期研修は個々に合った研修をおこなうため、研修1年目は育成面接を3・6・12ヶ月目におこなう。それ以降は6ヶ月ごとにおこなう。面接は研修評価用紙に事項を記入する。
- 中期研修は個々にあわせた研修をおこない、6ヶ月ごとに面接をおこなう。
- 研修に使用する評価用紙やレポートはファイルにまとめ、日常診療の中でも活用する。
資格取得
| セラピストマネージャー | 3名 |
| 認定理学療法士 | 2名 |
| 介護支援専門員 | 5名 |
| 3学会合同呼吸療法認定士 | 2名 |
| 住環境コーディネーター2級 | 4名 |
| 福祉プランナー | 3名 |
| 認知症ケア専門士 | 5名 |
| 認知症ライフパートナー2級 | 1名 |
| NST専門療法士 | 1名 |
| 医療クオリティマネージャー | 1名 |
| 離床プレアドバイザー3級 | 1名 |
| 両立支援コーディネーター | 2名 |
学会発表
| 2021年度 | |
|---|---|
| 全日本民医連学術運動交流集会 | 1名 |
| 道南学術運動交流集会 | 8名 |
| 第23回日本医療マネージメント学会学術総会 | 1名 |
| 函館市地域リハビリテーション研修会 | 1名 |
| 認知運動療法全国大会 | 1名 |
| J-HPHカンファレンス | 1名 |
| 2020年度 | |
| 道南学術運動交流集会 | 5名 |