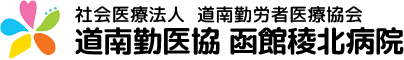検査科について
検査科は、患者さんの病気を診断し、適切な治療を行うために必要な検査を担当する部門です。
医師が正確な診断や治療方針を決めるための重要な情報を提供する役割を担っています。
また、治療の効果を確認したり、病気の重症度や回復の様子を調べるのにも役立ちます。
臨床検査には、大きく分けて2種類あります。
- 検体検査:血液や尿、便、痰、採取した臓器などを調べる検査
- 生理機能検査:機械を使って体の機能を調べる検査(例:心電図、脳波、超音波検査など)
これらの検査を行うのが臨床検査技師です。
現代の医療はチームで行われ、医師を中心にさまざまな専門職が協力して患者さんの診断や治療、回復を支えています。
検査科のスタッフもその一員として、日々努力を重ねています。
主な業務について
検体検査
生化学検査
血液中や尿中に含まれている蛋白成分・酵素・脂質・含窒素成分・電解質・糖代謝関連物質等のさまざまな成分を分析し、病気の診断、経過観察、治療効果の判定などに利用します。
血液検査
血液の固形成分である血球(赤血球、白血球、血小板) の数や血色素量などを調べる検査のことで、貧血や白血病、感染症などの診断に重要な検査です。
尿一般検査
古くから一般的に行われている、スクリーニングを目的とした尿の検査になります。「尿」は、体中を循環している血液が腎臓によって濾過されてつくられます。 このため、尿一般検査は尿がつくられる腎臓や尿路の異常を見つけることだけでは無く、全身の情報を得る事も出来ます。
生理機能検査
心電図検査
不整脈・心筋梗塞・狭心症などを診断する上で重要な検査です。
呼吸機能検査
喘息・肺線維症・肺気腫などを診断するのに有用な検査です。
FeNo(呼気一酸化窒素濃度測定)
吐き出した息に含まれる一酸化窒素(NO)の濃度を測定する検査です。
喘息の診断や治療効果測定、炎症コントロールの評価に利用されます。
振動病精査
振動障害の有無や程度を詳細に調べる検査です。主な検査としては、振動覚検査、皮膚温測定、握力測定、爪圧テスト、タッピング動作機能検査などがあります。
超音波検査
- 腹部領域(検査時間15分~30分程度)
肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓・膀胱・消化管などの臓器について大きさ形・内部組織の状態を観察し、急性・慢性炎症・悪性腫瘍の有無などを診断します。但し:膀胱・前立腺・子宮・卵巣観察時には排尿を我慢して頂く場合があります。 - 心臓領域(検査時間30分程度)
心臓内弁の状態の観察・血栓や腫瘍の有無の観察・心臓ポンプ機能(収縮拡張機能)把握・手術前の評価などに用いられます。 - 体表領域(甲状腺)(検査時間:15-30分程度)
臓器の大きさ・臓器内部状態・腫瘍の有無を観察します。 - 血管領域(頸動脈・下肢静脈)(検査時間:15-30分程度)
内視鏡検査について
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)は、口や鼻から内視鏡を挿入し、食道・胃・十二指腸の内側を直接観察する検査です。
がんの有無を調べるだけでなく、発見された病変の深さや広がりを確認し、治療方針の決定にも役立ちます。
また、必要に応じて鉗子口から医療器具を挿入し、組織の一部を採取することもあります。
通常、観察のみのスクリーニング検査であれば5分程度で終了しますが、処置内容により時間が延びる場合があります。
前処置を含めた所要時間はおおよそ20~30分程度です。
当院では、より苦痛の少ない経鼻内視鏡(鼻から挿入するタイプ)も取り入れており、患者さまの希望や状態に応じて検査方法を選択しています。
注意事項
検査前日は20時までに消化の良い食事を済ませ、それ以降の飲食はお控えください。揚げ物など脂っこい料理は避けていただくようお願いします。検査当日は朝食や牛乳・ジュースなども控えていただきますが、水やお茶は検査1時間前までお飲みいただけます。
朝のお薬については、事前に看護師より説明があります。
内視鏡検査に伴う偶発症
上部消化管内視鏡検査では、ごくまれに消化管出血や穿孔(腸や胃に穴があくこと)などの偶発症が起こる可能性があります。
これらが生じた場合は、入院や緊急の処置、手術が必要になることもあります。
発生頻度は全国集計で0.012%と報告されています(日本消化器内視鏡学会)より。
下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)
下部消化管内視鏡検査(大腸内視鏡)は、直径約1cmの内視鏡を肛門から挿入し、大腸の内側を観察する検査です。
病変の有無だけでなく、がんの深さや広がりを確認し、治療方針の決定にも役立ちます。
必要に応じて、鉗子口から医療器具を挿入し、組織の採取やポリープの切除などの処置を行うこともあります。
検査時間はおおよそ10分から30分程度です。
注意事項
検査当日ご来院後に腸管洗浄剤を内服していただきます。
事前に服用していただくお薬や食事に関しては、看護師よりあらかじめ説明があります。
大腸内視鏡検査では、ごくまれに出血や穿孔(腸に穴があくこと)などの偶発症が起こることがあります。
また、検査前に服用する下剤の影響で、腹痛や出血、穿孔を引き起こす場合もあります。
これらの症状が現れた場合には、入院や緊急の処置、手術が必要になることがあります。
大腸内視鏡検査および治療に伴う偶発症の発生頻度は、全国集計で0.011%(約9,000人に1人)と報告されています。(日本消化器内視鏡学会より)