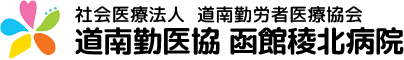リハビリテーション科での専門研修
リハビリテーション科では、地域医療、家庭医療をめざす医師、高齢者医療に関心のある医師が、短期間研修でリハビリテーションを学ぶことができます。
また、09年度中にはリハビリテーション認定研修施設を取得済みです。稜北病院での研修によって、リハビリテーション医学会の認定医の受験資格をえることができます。
(日本リハビリテーション医学会)
道南勤医協リハビリ科専門研修の特長は大きく二つあります。
- 地域医療、家庭医療や高齢者医療を支えるリハビリテーションの技術、考え方をしっかり学ぶことができます。
- リハビリテーション医の専門資格取得と地域医療研修を同時に行うことができます。
高齢者医療、地域医療を支えるリハビリテーションの技術、考え方をしっかり学ぶことができます
リハビリテーション医療の特徴
リハビリテーション医療には、他の専門分野とちがって、次のような特徴があります。
- 「疾病」の医学ではなく「障害」の医学、QOLの医学である
- 3つの運動領域(上肢をつかった操作活動、移動、摂食排泄)と2つの認知領域(コミュニケーションと判断)を主にとりあつかっている
- 障害を機能面(例:下肢の麻痺)、能力面(例:歩行障害)、ハンディキャップ(例:バスに乗れない)、心理的障害(例:生きがいがない)の各レベルからとらえる
- 社会保障制度全般に習熟できる
いずれも地域医療、家庭医療や高齢者医療を展開するときに大いに役立つ考え方、知識だと思います。
疾患・障害別の研修分野
疾患・障害別の研修分野としては次のようなものがあげられます。
- 脳卒中、その他の脳疾患(脳外傷など)
- 脊髄損傷、その他の脊髄疾患(二分脊椎など)
- 関節リウマチ、その他骨関節疾患(外傷含む)
- 脳性麻痺、その他の小児疾患
- 神経及び筋疾患
- 切断
- 呼吸器・循環器疾患
- その他(悪性腫瘍、末梢循環障害、熱傷など)
これらの疾患・障害にかかわる診断と治療には次のような分野があります。
診断学:画像診断(ビデオ嚥下造影など、下図)、電器生理学的診断(脳波、筋電図ふくむ)、各障害の評価(意識、運動機能、言語、その他の高次脳機能 など)
治療学:廃用症候群、褥瘡予防・経管栄養ふくむ栄養管理、障害の予後予測、摂食嚥下訓練、排泄管理、家屋改造、義肢装具学、リハ機器、神経筋ブロック治療など

リハビリテーション医の専門資格取得と地域医療研修を同時に行うことができます
稜北病院には、2名のリハビリテーション医学会認定専門医がいます(鎌倉嘉一郎 リハビリテーション科科長、堀口信 同医師)。北海道内でも複数の専門医がいる施設は限られています。
堀口信医師は失語症、高次脳機能障害、義肢装具などを得意分野としています。
鎌倉嘉一郎医師は回復期リハビリ病棟の専任医師で、脳卒中のリハビリ全般を扱っています。病院では嚥下造影検査を担当しています。
リハビリ科の研修は主に回復期リハビリ病棟で行います。
回復期リハビリ病棟は市内の医療介護施設や稜北病院の外来、在宅サービスと密接に連携しています。
とくに脳卒中のリハビリでは連携協議会に参加して、市内の急性期病院脳外科と連携をつよめています。
リハビリ科の研修をうけながら、同時に函館市内での在宅医療研修、江差診療所での地域医療研修をうけることもできます。